さて、今日はですね。
今後、後輩や学生の指導にあたる予定の先輩セラピストの皆さんに向けた内容でございます。
特に、レポートなり症例発表における抄録の『考察』部分ですね。
ここを指導するときのポイントについて、少し解説していこうかななんて思っております。
というのも、考察の指導は「着眼点が絞りにくくフィードバックに困っちゃう」という方の相談を頻繁に頂くからです。
なので今回は…
 きんたろー
きんたろー考察は大体このパターンでミスってることが多いよ〜
という、このあたりについてもうクリティカルにゴン詰めしていこうかなと思います。
ただ、先輩セラピストさんに向けた内容とはいえ…
今回の記事は、考察を書くときに良くある失敗パターンについて解説するので、先輩セラピストの皆さんにはもちろんですが、これから考察を書かなくちゃいけない人にもかなり参考になる内容かと思います。
ぜひ、最後までご覧ください!
【先輩セラピストの皆さーん】症例発表時『考察』を見る際のポイント
『考察』でよく見る失敗パターン
『考察』において…
「〜らは××を行うと良い」と述べていることから、方法Aを実施したところ最終評価では歩行に改善が見られた。
大体、考察で良くあるケースってこのパターンで…
- こういうこと(事実)がありました
- その事実に対して〜らは「◯◯と述べていました」
- 「だから私も◯◯を行いました」その結果〜〜になりました
みたいな、こういうロジックですね。
で、このロジックの何が問題なのか?(問題があるからこれを例に出してるわけ)
結論、『考察が事実の要約にしかなっていない』ということですね。
「考察が事実の要約にしかなっていない」とは、つまるところ…
自分の『解釈』が全く含まれていないんです。
含まれているっぽく見えるんだけど全然含まれていないんです。この考察には。
考察って本来は、得られた事実(結果)に対して自分がどう考えたのかという、そういう解釈が欲しいわけです。
なので、考察部分に関しては事実をただ並べて終わりではなく、大事なのは「あなたはどう考えていますか?」というあなた自身の考えを記して欲しいんですね。
極端なことを言うと、目に見える事実(歩行障害がある、筋力低下がある、ROM制限がある。など)をただ羅列するだけなら誰でもできるんです。
しかし、“あなたの考え”は誰にでも出せる結論ではありません。
発表に至るまでに得た思考は、あなた自身がこれまで臨床で試行錯誤を繰り返しながら培ってきた完全オリジナルなものであるはずです。
『結果』は、事実だけを書くところなのであなたの想いを組み入れる余地はありませんが『考察』ではそれが唯一込められる場所です。
だからこそ考察では、臨床を通してあなたが考えた思考を全て出していく必要があるわけです。


『自分の考え』でOKならトンチンカンな事を言って良いかというと流石にそれはダメ
考察は、自分の考えを述べるところ。
これ自体は間違いがないんですが一方で、『自分の考えを伝えるときのルール』というのはちゃんと設計されているので、ここは抑えておきたいところです。
そのルールというのが…
『主張を根拠で支える』ということです。自分の考えを主張する際には、このルールは絶対に守らなければなりません。
なぜならば、根拠がない状態にも関わらず自分が言いたいことだけ言ってもそれでは当然『信憑性』が薄いからです。
だからこそ、その主張(自分はこう考える)をするのであれば、その根拠となるような客観的な事実、そして科学的な根拠をすり合わせて言及する必要があります。
【考察のポイント】引用論文は根拠の補填にしかならない
また考察というのは、完全に言い切るというのが行えないケースが多く、多くは「こういう可能性がある」「こうではないかと考える」というような推論に収束するパターンが多いですが、これにおいても可能性だからといって突拍子もないことを言っていいかというとそれは違います。
先ほど同様に…
私は◯◯だと考えています(主張)。なぜならば、これら事実が示す徴候はその可能性を示唆しているからであり(根拠)、〜らもそのように述べているからです(根拠の補填)。
こういった形になるのが理想です。
ここでのポイントは、「引用文献は根拠の補填にしかならないという点」です。
引用文献というのは、基本的に自分自身の主張を支える根拠の補填的な役割にしかなりません。
つまり、メインとなる根拠には到底なり得ないのです。
よく引用文献そのものが、あたかも自分自身の主張を支えるメイン根拠であるというような感じで、切り札的に出してくる人がいますがこれは大きな誤りです。
学生さんや新人さんの症例発表などを見ると、このパターンが非常に多いのでここは注意深く観察しておく必要があると感じています。
引用論文がメインになっちゃうワケ
引用論文がドカンとメイン根拠になっちゃう一つの理由は、「まだまだ知識不足で自分自身の主張に自信が持てないから」というのがあると思っていて、引用文献の力を借りて主張を正当化したくなるんだと思っています。(気持ちはわかる)
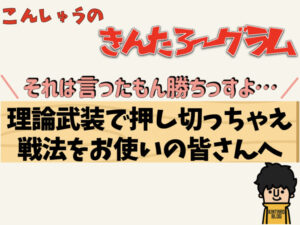
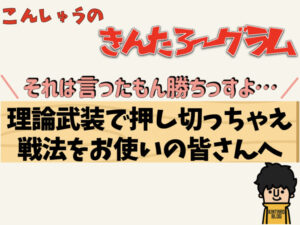
考察のポイントまとめ
というわけで、以上が考察を見る(書くときも)際のポイントになります。
考察が事実の要約になっていたり、引用論文だけで塗り固められた考察になっているケースは案外多いので、このあたりをしっかりと見ていけたら良いのではないかと思います。
考察を丁寧にまとめてくことで、「自分は臨床でどのように考えたのか?」という思考の整理が行えるので、ここは手を抜かずしっかり汗をかいて頂きたいなと個人的には思っています。
それでは、明日もいい仕事していきましょ!
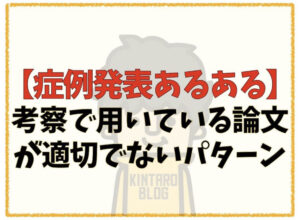
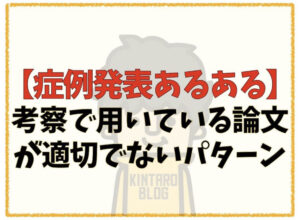


コメント