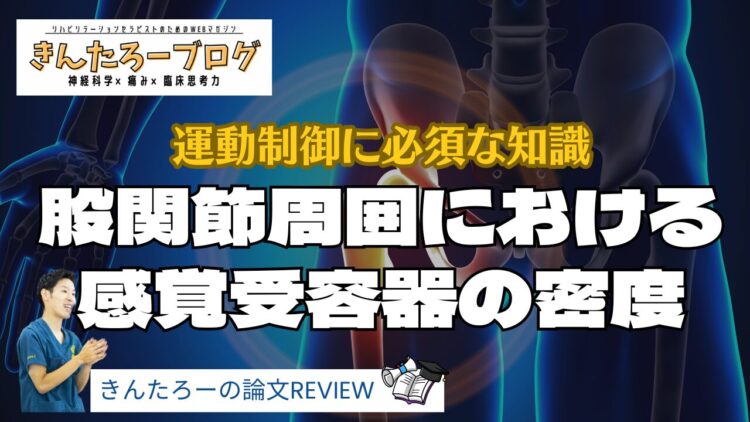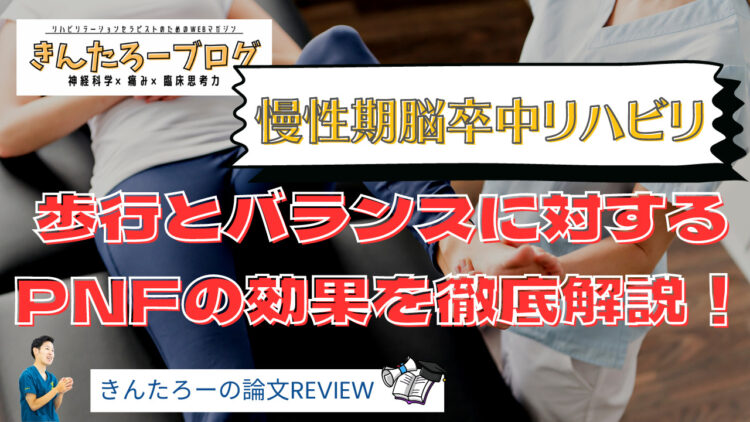神経科学– category –
-

【2024年最新】股関節周囲における感覚受容器(メカノレセプター)の密度を解説!
『感覚受容器』あるいは『メカノレセプター』というワードは、リハビリテーション業界の中で生きているとそれはもう聞き飽きるほど耳に入ってくる単語の一つです。 使われる場面としては…感覚の問題を説明する時だったり、痛みの問題を説明する時だったり... -

【最新版】慢性脳卒中患者の歩行とバランスの改善に関する固有受容神経筋促進法(PNF)の効果
この記事では、私たちリハビリテーションセラピストが日々の臨床で直面する、「慢性期脳卒中患者様に対するリハビリテーション介入の効果」について解説していきます。 その中でも今回シェアしたい介入方法は『Proprioceptive Neuromuscular Facilitation... -

【2023年最新】ペンフィールドの脳内一次運動野におけるホムンクルスの概念が刷新!
「脳内には綺麗にマッピングされたホムンクルスがあるよね」 これは、おそらく殆どのセラピストの皆さんの中である程度一致する見解だと思います。 用語解説『ホムンクルス』 ホムンクルスとは、大脳皮質一次運動野(M1)と一次体性感覚野(S1)において、... -

【筋膜神経学】先行研究で明らかになった筋膜の解剖学と神経支配まとめ
筋膜は、筋肉やその他の構造物を覆い人体全体をつなげる重要な組織です。 最近の研究では、筋膜の痛覚受容器が痛みや機能障害に関与している可能性が示唆されています。 この記事では、筋膜の痛覚受容器に関する研究結果を参考に日々のリハビリテーション... -

弓道におけるイップスの有病率となりやすい人の特徴について解説
この記事では、弓道におけるイップスの有病率やその原因について、2021年に発表された研究論文をもとに解説していきます。 イップスについては、この記事以外にもいくつか解説しているのでご興味ある方は併せてご覧ください。 イップスに関する記事一覧 【... -

【これを見れば網羅できる!】二点識別覚の意義や実施方法、カットオフ値などを徹底解説
この記事では、以下の項目について解説しています。 この記事で分かること 二点識別覚は何を検査しているのか? 二点識別覚の実施方法と注意点 二点識別覚を行っている最中の脳活動 二点識別覚のカットオフ値(知見あり) 二点識別覚と慢性疼痛の関係 これ... -

【ゴルファー1000人以上に聞いた】イップスの原因に最も関連するのはこの2つ!
この記事では… イップスとはどのような病態なのか? イップスの原因となる2つの因子 ゴルフにて最もイップスが生じやすい瞬間 イップスが発生する確率が高いゴルフクラブ これらについて、昨年発表された論文をもとに解説しています。 ぜひ、最後までご覧... -

【脳卒中評価法】Functional Assessment for Control of Trunk:FACTについて分かりやすく解説!
脳卒後遺症患者様に対して体幹機能を評価をする場面ってよくあるかと思います。 その際、用いる評価バッテリーには『Stroke Impairment Assessment Set:SIAS』や『Trunk Control Test:TCT』、『Trunk Impairment Scale:TIS』などがあります。 これらの評価... -

【ゴルファー必見】イップスの有病率となりやすい人の4つの特徴
何らかのスポーツを続けていると、自分もしくは周囲(チームメイトなど)のメンバーの中で『イップス』という問題を抱えるケースがあります。 このイップスという用語自体が一番浸透しているのはおそらく野球だろうと思いますが、実際にはゴルフやピアノ、... -

【無料】DNSアプローチの実技が学べる方法をご紹介
この記事では、「DNSアプローチの方法論をどうやって学ぶか?」ということについて、僕が実際に行っているDNSアプローチの学習方法についてご紹介したいと思います。 臨床においてDNSの考え方を取り入れたアプローチは、(病態解釈に基づいていれば)すご...