さて、いきなりですが皆さんに質問です。
皆さんは、症例発表を行う時などにレジュメや抄録を書くと思いますが、その際に『結果』と『考察』の違いが理解できていますか?
実は、病院内で行われる症例発表や学生の皆様が実習後に行う症例発表会なんかに参加させていただくと、案外この『結果』と『考察』が混同している内容を見かけることがあります。
そこで、今日はこの両者の違いについて説明していきたいと思います。
これから、症例発表の準備に取り掛かる方必見です!
症例発表における『結果』と『考察』の違い
症例発表における『結果』とは
結果とは、ある物事を行った後に生じた現象、状況、物象を表す言葉
『wikipedia』より
『結果』とは、この定義からも分かる様に、原則として”事実”でなければなりません。
事実とは、良い結果も悪い結果も包み隠さず表現することです。
つまり症例発表でいうならば、様々な評価や治療アプローチの結果どうなったかというのを、着色せずあるがままに書き出す作業がこれにあたります。
となると、レジュメなどに『結果』を書いていく際、最も大切なことは何か?
それは、自分の解釈を混入させない事です。
先程から述べているように、『結果』というのは生じている事実のみから得られる情報です。
そこに、自分の解釈を入れてしまうと事実が歪み(多くは自分の意図したい方向に事実を歪ませる)、結果が変わってしまう可能性があります。
これがよく現れるのが、特に自分にとって良くない(意図していない)結果が出た時です。
隠したくなる気持ちになるとは思いますが、そんな時こそ、その事実をきちんと公表することが大切です。
なぜなら、そうすることで『なぜ、自分が立てた仮説と異なる結果になったのか』というのを考えるきっかけになるからです。
上手くいかなかった時こそ、簡単に「ダメだった次」ではなく、その原因を考える癖を身につけておく必要があります。
そのために、『結果』の部分には自分の推論は含まず、事実のみを書くように意識しましょう。
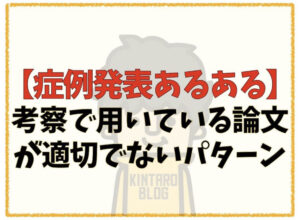
症例発表における『考察』とは
物事を明らかにするためによく考えること
『Google』より
さて、一方で考察というのは、この定義にもあるようによく考えてアウトプットを出すことです。
ただ、考えてアウトプットを出すというとよく誤解しがちになりやすいことがあり、それが『感想』や『事実の羅列』に終止してしまう事です。
『考察』とは、その名の通りよく考えて察することであり、以下のようなただ単に出ている結果をまとめた『要約』ではありません。
 セラピスト
セラピスト〇〇の評価を行い、△△という仮説の元、□□という治療を実施したが今回の治療期間では変化が見られませんでした!
このセラピストの発言は、結果をただ羅列しているだけで考察にはなっていません。
考察を行う際に最も大切なことというのは”結果に対してあなたがどう考えたか”です。
例えば、先ほど『結果』の話し際にも触れましたが、もし仮に自分が意図しない結果が得られた場合に「考察してください」と言われたら何をすればよいでしょうか。
答えは、『なぜ、そのような意図しない結果が生じたのか?』というのを自分なりに考えてアウトプットを出すことです。
そうするとこれもまた誤解しやすいのが、引用論文の使い方です。
僕が個人的によく引用論文の使い方に関して違和感を感じる考察がこちらです。
誤った論文の用い方
誤った論文の用い方ですが、結論これは『結果に対する根拠づけが引用論文のみしかない』というやつです。
これのどこに問題があるのか。
その理由は、作成者の考えが一切含まれていないからです。
例えば、得られた結果(事実)があったとして、それに対する根拠が「~らが述べているから…」と引用論文のみで結論づけている考察があったとします。
さて、果たしてここに作成者の考えは含まれているでしょうか?
さらにいえば、一生懸命”考えた”と言えるでしょうか?
これだと、結果を肯定する論文を後付けで探しさえすれば考えなくとも結論が言えてしまいます。
これでは考察と言えないことに加え、作成者の意図や考えが聴衆に伝わらないため議論もしづらい内容となってしまいます。
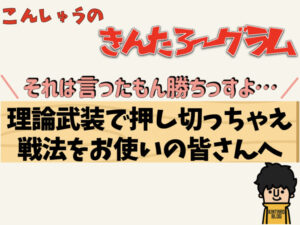
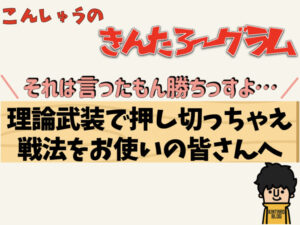
『結果』には含ませず『考察』に含ませてよいもの
それが『解釈』です。
これは論理的であるという前提がもちろん必要ですが、『考察』の場合は様々な結果を解釈して自分なりの考えをアウトプットすることが許されています。
よって、どれだけ自分の考えを書き出すかというのがとても重要になり、かつバリューのあるテーマになります。
さて、以上が『結果』と『考察』の違いです。
ざっくりとでしたが、いかがでしたでしょうか?
『結果と考察の違い』まとめ
それでは、今回お伝えしてきた内容のポイントをおさらいします。
- 『結果』を書く上で大切なことは、事実と解釈を混同させないこと
- 『結果』は事実、『考察』は解釈(自分の考え)
- 『考察』を行う時は”事実の羅列”に終止しないこと
- 結果の裏付け(根拠)を引用論文に全投げしないこと(自分の考えを含ませる)
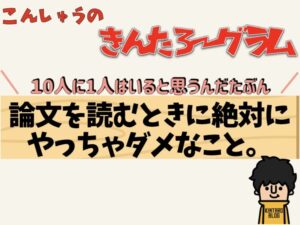
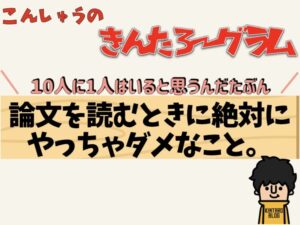


コメント