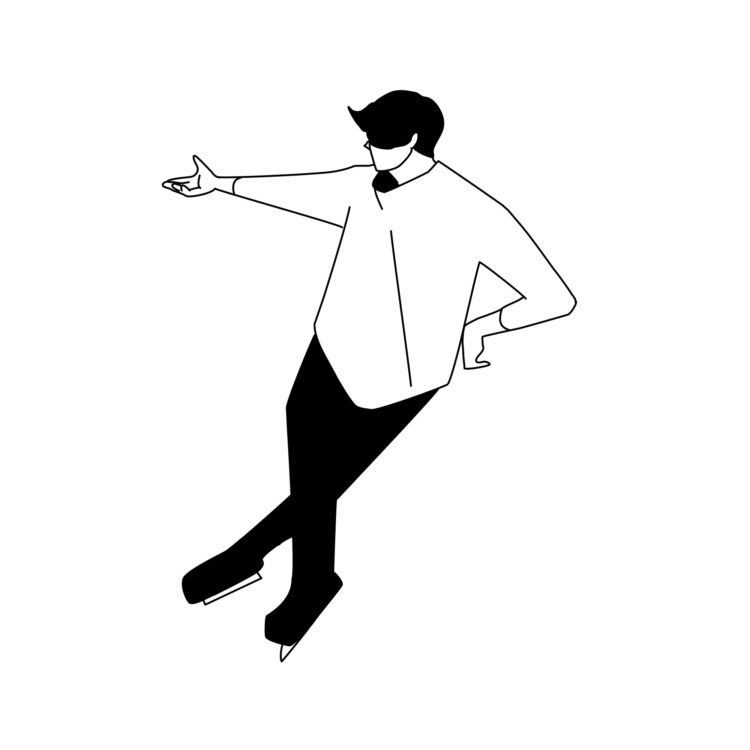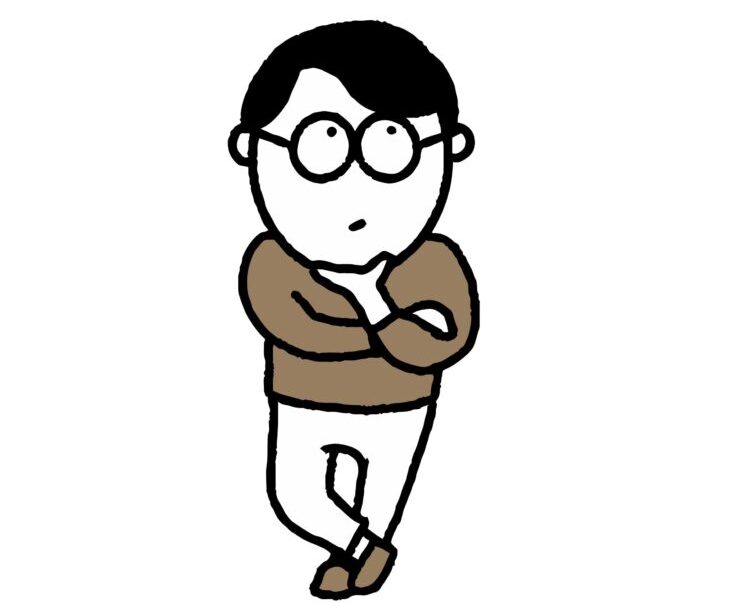2018年4月– date –
-

筋シナジーパターンと運動制御理論
ヒトはあまりにも冗長(莫大)な運動の自由度をもっています。そのため、一つの場面設定を設けただけでもそれに対応する運動の選択は何通りも存在します。 例えば、『テーブルの上に置いてあるコップを手に取る』という行為ひとつとってみても、コップに上... -

運動制御理論とリハビリテーション
今回は『運動制御とリハビリテーション』というテーマで、私たち人が四肢を円滑に動かせるその仕組みについて解説していきたいと思います。 この記事を読めば… ヒトの運動制御がどのように行われているかを学べる認知神経学的と生態心理学的な運動制御の考... -

日本の手技の覇権争いは一体いつまで続くのだろう
【日本の手技の覇権争いは一体いつまで続くのだろう】 さて現在日本には手技や、~療法といったものが沢山あります。 それに伴って、そういったセミナーも開催されているところが多いです。 もちろん各種それぞれの手技や理論体系が間違っているといいたい... -

【シナジーパターン】歩行中の筋活動のつながりを分かりやすく解説
ヒトの歩行は神経系の関与はもちろん、関節やそこに付着している筋肉が絶妙なタイミングで活動することによって実現できているわけですが、この歩行中に参加する筋肉の数というのは約25筋ほどであると言われています。(Ivanenko,2004) このように、数多... -

「こころ」を見れるセラピストになるために
【「こころ」を見れるセラピストになるために】 私達セラピストは患者様に対して「リハビリテーション」を提供しますが、その際ただ単に「運動療法」のみを行っているわけではありませんよね。 運動療法を提供する前に セラピストと患者 という場合におい... -

患者様とどのように関われば良いでしょうか?
私達セラピストは患者様に対して、治療を行う場合もあれば、訓練をする場合もあれば、運動指導をする場合もあります。 ですので、立場的にはなんとなくの空気感としてセラピストが「先生」、患者様が「生徒」という構図が出来上がります。 これは、決して... -

運動イメージとは?また、どうやってリハビリに応用する?
近年、『運動イメージ』がリハビリテーションの中で活用されてきていることをご存知でしょうか? 従来のリハビリテーションの方法といえば、徒手による介入や装具による介入、電気などの物理療法機器などを用いた介入が有名ですが、最近はこれら方法の中に...
1